
NPO法人
壱岐しま自慢プロジェクト
壱岐しま自慢プロジェクト
有償ガイドページへ
地層で見る壱岐の歴史①
地層で見る壱岐の歴史②
地層で見る壱岐の歴史③
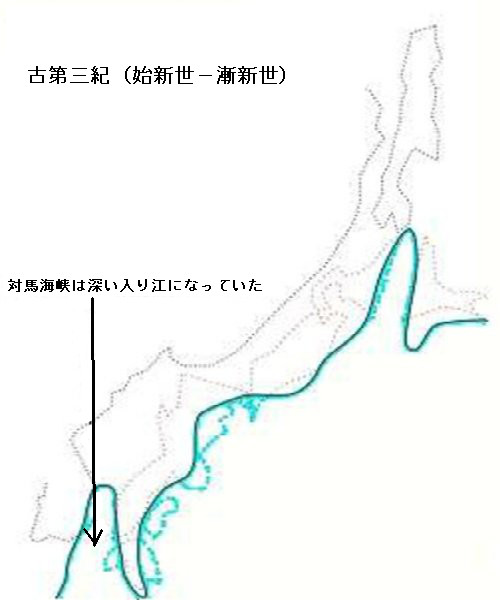 |
| 図1 HPの地球講座(2. 地層と岩石)より |
 |
 |
| 図2-A 壱岐の土台石と言われる深層部だった勝本層 | 図2-B 土台石の深層部では頁岩が多い |
 |
 |
| 図2-C 上層部だった一般的な勝本層 | 図2-D 一般的な勝本層の互層構造 |
 |
 |
| 図2-E 壱岐の土台石は色が濃く薄く剥離する | 図3-F 壱岐の土台石はこのように薄く剥離する |
ページトップへ